城の石垣の学び(4)HOBBY
安山岩の基盤の上に築城は? 江戸城は?

江戸城
江戸城は、防御の面から自然石を積み上げた「野面積み」は、石垣を上りやすいため見る
ことができない。「打込み接ぎ」や「切込み
接ぎ」が見られる。石垣の石は、石材が豊富
にとれ、海運に便利な伊豆半島の安山岩が主
に使われている。また、白く見える石は、小
豆島石(御影石)と呼ばれる花崗岩。
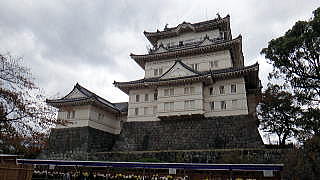
小田原城
中世の北条氏の築いた小田原城は、土塁空堀で構成されていたが、稲葉正勝が入城した1
632年以降に城の整備が進められ、石垣も
築造された。石材は、箱根火山の溶岩で(輝
石)安山岩がみられる。小田原市制20周年
記念として三重四階・層塔型の江戸時代の天
守が再建されている。
(2013 小田原城 撮影:じっさま)

甲府城
武田氏滅亡後、甲斐国が豊臣秀吉の支配下にあった1590~1600年頃築城された。
石垣は巨岩をほとんど加工することなく積ん
でいく野面積みで造られている。地表に露出
した安山岩の岩盤の上に築かれた城の石垣の
石材は、城内や城北の愛宕山で採取された安
山岩でできている。
(2018 甲府城 撮影:じっさま)

松本城
城は扇状地の端にある軟弱地盤に建てられ、16本の木の丸太が土台支持の杭(直径39
cm、長さ5m)として1000トンの大天
守を支えている。石垣の築石、間詰石には閃
緑班岩が、裏込石のレキには安山岩、緑色凝
灰岩など付近を流れる女鳥羽川などに多く見
られる石が用いられている。
(2014 松本城夜景 撮影:じっさま)
じっさまの館
〒44-1181
現世長命市 天国区願望町1-2-3
TEL :以心伝心(局)0008